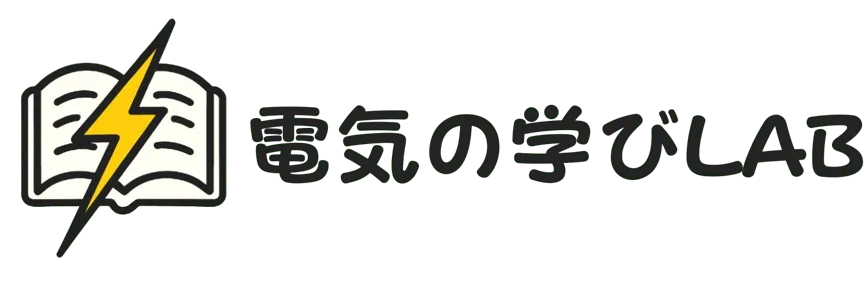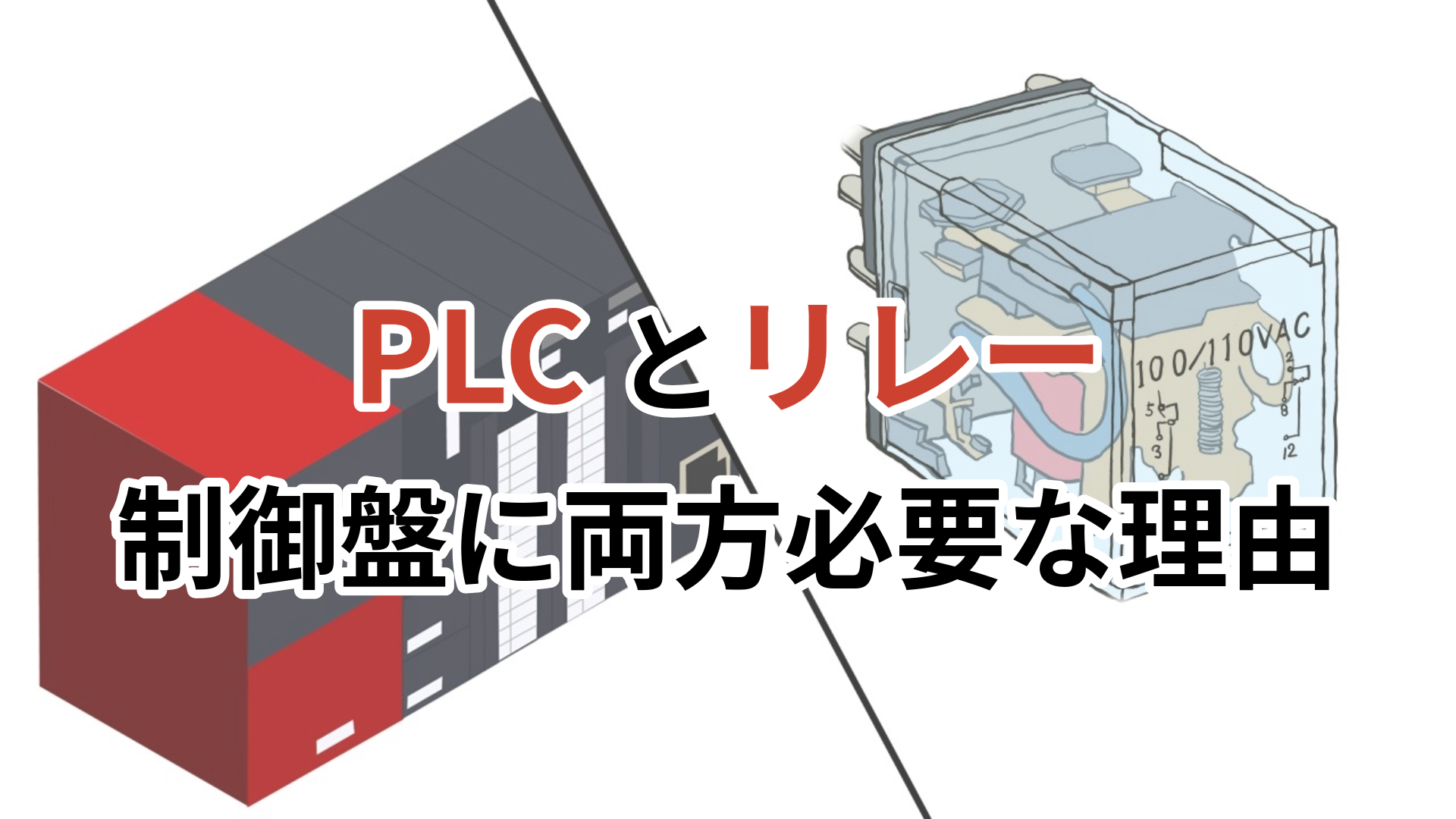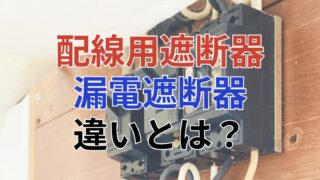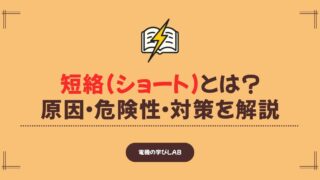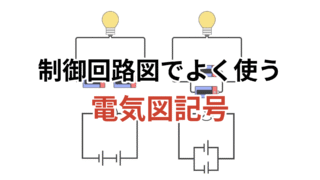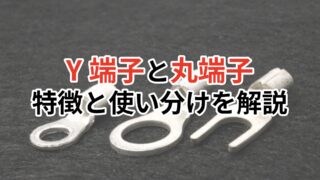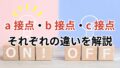制御盤を初めて開けたとき、「PLCを使っていてもなぜリレーを使うのか?」と不思議に思った経験はありませんか?
私自身、新人時代に「PLCはリレーの代わりになる装置だ」と習っていたため、目の前の制御盤に大量のリレーがあるのを見て疑問を抱きました。
本記事では、制御盤にPLCとリレー両方が必要とされる理由をわかりやすく解説します。
PLCとリレーなぜ両方必要?
なぜ、PLCが普及した今でもPLCとリレーは共存しているのでしょうか?
結論から言うと、
PLCだけではリレーの役割を全て担えないため、制御盤には両方必要なのです。
PLCとリレーは「リレー受け」をすることで、それぞれの利点を活かして明確に使い分けがされています。
以下では、それぞれの役割の違いや使い分けについて解説していきます。
そもそもPLCとは?

引用:シーケンサ MELSEC-Qシリーズ | 三菱電機FA
PLC(Programmable Logic Controller)は、工場や設備の動作をプログラムで制御するための装置です。
従来、リレー回路で「順序制御」や「論理制御」を行っていたものを、プログラムに置き換えることで配線を大幅に減らし、柔軟に動作を変更できるようになりました。
例えば、
- スタートボタンを押すとモーターが回転
- センサーが反応すると停止
- 異常時にはアラームを出す
といった一連の動作を制御するには、リレーでは複雑な配線をする必要がありましたが、PLCではプログラムを書き換えるだけで済みます。
そもそもリレーとは?

リレーは「電気信号によって接点を開閉するスイッチ」のことです。弱い電気信号で大きな電流をオンオフできるため、工場の制御回路には欠かせません。
種類としては、
- 電磁リレー
コイルに電流を流すと接点が動作して通電する - ソリッドステートリレー(SSR)
半導体でスイッチングしてるリレー
などがあります。
PLCが登場する前は、数百個のリレーを組み合わせて制御盤を構築していました。現在も、信号の絶縁や外部機器の制御に幅広く利用されています。
【疑問】PLCがあればリレーは必要ない?
私が何も知らない新人の頃、先輩からこう習いました。
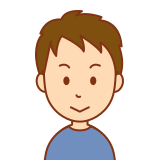
「PLCはリレーの代わりになる装置だよ」
この言葉だけを聞くと、「じゃあPLCがあればリレーは要らないはず」と思ってしまいますよね。
しかし実際の制御盤を見てみると、PLCの横には多量のリレーが並んでいます。
ここに多くの新人が抱える以下のような疑問があります。

(新人時代)
制御盤にはPLCとリレーが両方あるけど、役割が被ってない?
PLCとリレー両方必要な理由
冒頭にも述べたように、PLCとリレーは明確に使い分けがされています。
以下では、PLCによって柔軟に制御回路を組むことが可能になった現在でも、制御盤にリレーが必要な理由5つを解説します。
1. PLCの出力電流は小さい
PLCの出力(DO:デジタル出力)は、基本的に小さな電流しか流せません。
例えば、1点あたり 0.5A程度が一般的です。
一方で、実際に制御する機器(ランプ、電磁弁、モーターなど)は24Vや200Vなど、もっと大きな電流が必要です。
そのため、PLCから信号を直接送っても機器を駆動させることができません。
実際の制御盤では、制御回路のリレーコイルに電流を流し、動力回路のリレー接点をONすることで、制御回路と動力回路を隔離しながら小さい電流で機器を動かしています。。
このような手法を「リレー受け」と言ったりします。
2. 電気的な絶縁が必要
1.ではPLCから信号を出力する場合にリレー受けが必要と説明しました。同様に、PLCに信号を入力する場合にもリレー受けをする必要があります。
制御回路に流れるDC24Vの電流を直接PLCに入力すると、故障や誤作動のリスクがあります。これは、外部機器からノイズや瞬間的な高電圧が直接PLCに流れてくるためです。
PLCは高価であり、制御の中枢的な役割を担っているので故障させる訳にはいきません。
そこで、リレー受けをすることでリレーを絶縁のバッファとして利用します。
PLC出力 →リレーコイル→リレー接点 → 外部機器を制御
スイッチなどの入力機器をONにするとリレーコイルに電気が流れます。すると、PLCに接続されたリレー接点が通電してPLCに信号を入力することができます。
このとき、スイッチとPLCは電気的には別回路で構成されています。よって、PLC本体を動力回路と離して守る役割を果たします。
3. 接点の増設・分岐ができる
PLCの出力点数は限られています。
しかし、制御盤の中では「1つの信号を複数の機器で利用したい」場面がよくあります。
例えば:
1つの異常信号を「警報ランプ」「ブザー」「管理システム」へ同時に送る
こうした場合、PLCから直接複数に分けるのは困難です。
しかしリレーを介して接点を増やすことで、PLCの小さい電流でも信号を自在に分岐できます。
4. 安全回路・非常停止回路に必須
非常停止回路など、安全性に直結する制御は リレーや接触器でのハード回路が基本です。
なぜなら、PLCはプログラム次第で誤作動や停止の可能性があるため、
「人の命を守る制御はPLC任せにしない」ことが電気制御の基本だからです。
そのため、安全回路ではリレーや安全リレーを多用します。
5. メンテナンス性・現場対応
リレーは目視で動作が確認しやすく、交換も容易です。
現場で「この接点が動いているか」をランプ表示や透明カバー越しに確認できる 故障時には数百円~数千円で簡単に交換できる
PLC内部のトラブルはプログラム解析が必要ですが、リレーなら電気的にシンプルで分かりやすいため、現場の保全担当者にも扱いやすいのです。
実際の制御盤での役割分担
制御盤ではPLCとリレーは、以下のような役割分担がされています。
PLC:論理制御・順序制御の中枢。配線を減らし、柔軟にプログラムを変更できる。
リレー:出力の増幅、絶縁、接点の分岐、安全回路、現場対応のしやすさ。
つまり、PLCがリレーの一部の役割を置き換えたものの、リレーにしかできない役割が今も多く残っているのです。
私自身、新人時代に制御盤を見て「リレーってまだこんな大量に使ってるんだ!」と驚きました。ですが、先輩方に理由を教えてもらう中で、次のように理解できました。
PLCは頭脳、リレーは手足のような存在で、両方が揃ってはじめて安全で安定した制御ができる!リレー受けという手段で制御回路と動力回路を隔離しているんだと学びました。
この学びは、今でも設計や現場対応の際に役立っています。
まとめ

制御盤にPLCとリレーが両方必要な理由は、次の通りです。
- PLC出力では大きな電流を扱えない
- PLCを守る絶縁の役割
- 信号の分岐・増設が必要
- 安全回路にはリレーが必須
- メンテナンス性の高さ
新人の頃は「PLCがあればリレーは不要」と思いがちですが、実際には互いに補完し合う存在です。
制御盤を理解する第一歩として、PLCとリレーの役割の違いをしっかり押さえておくことが大切です。