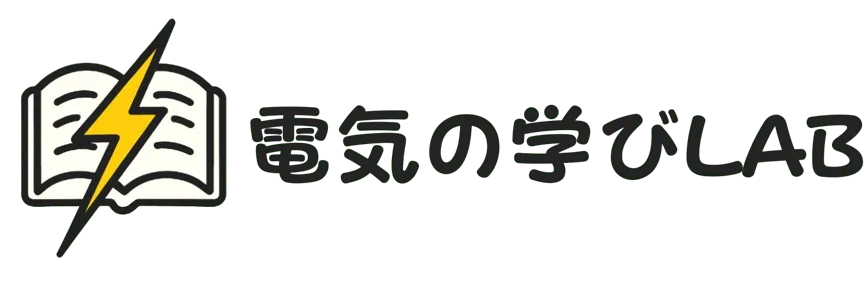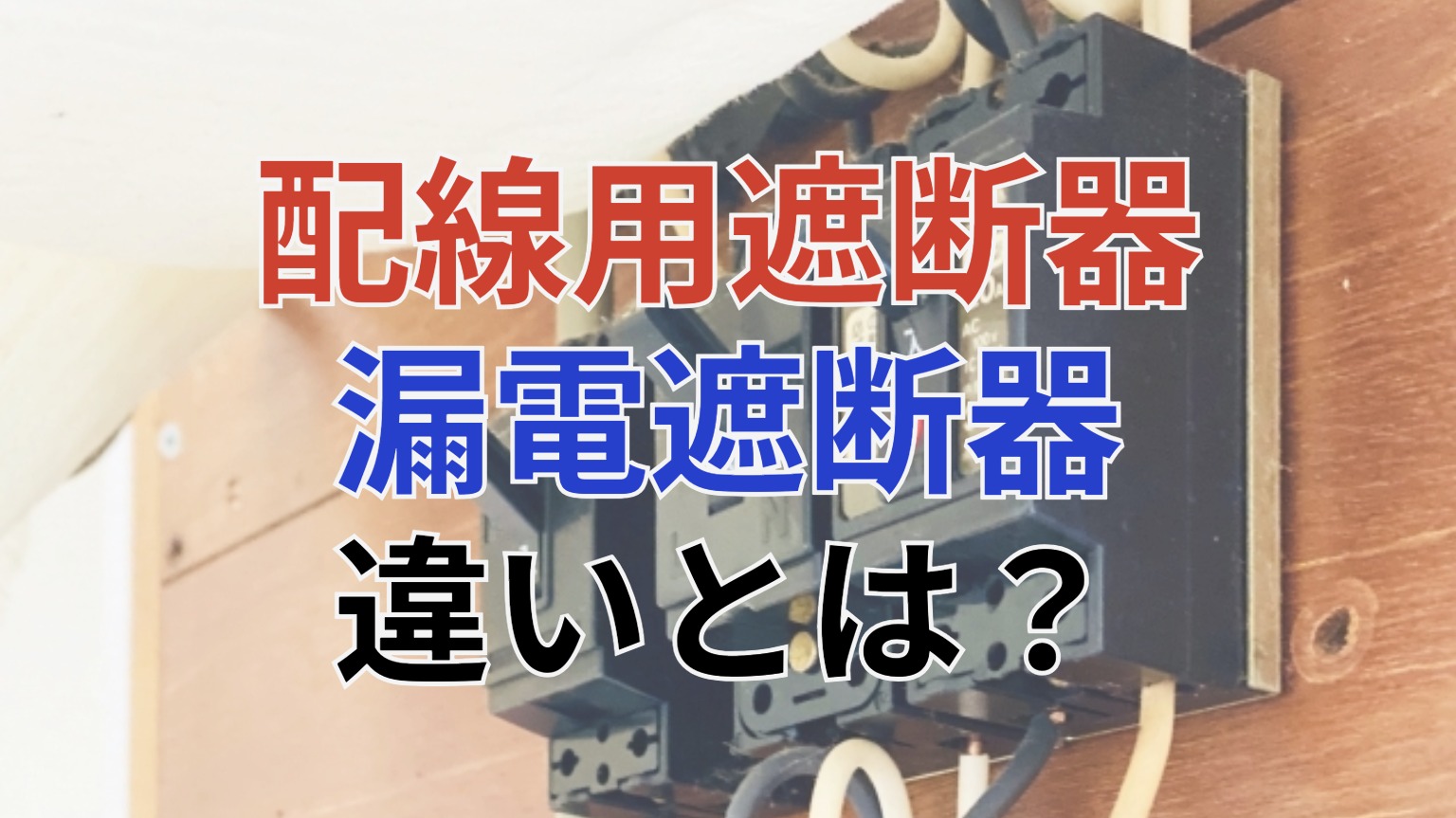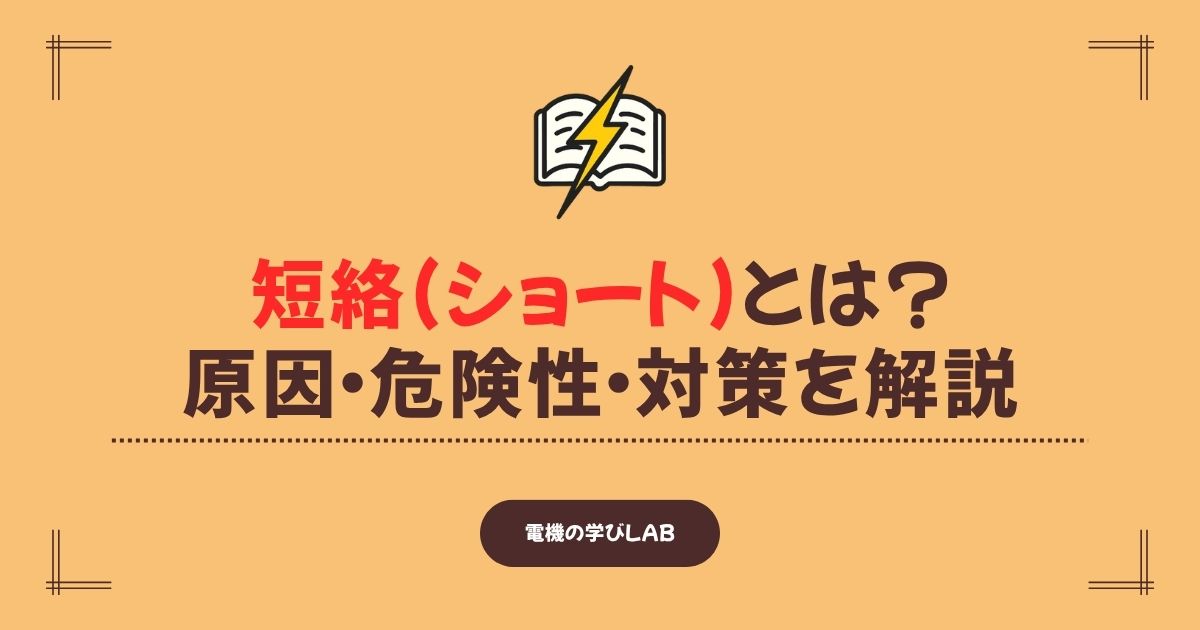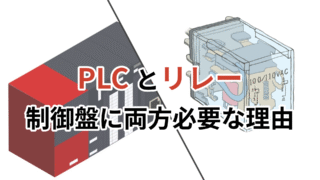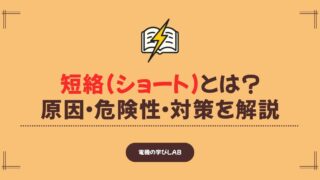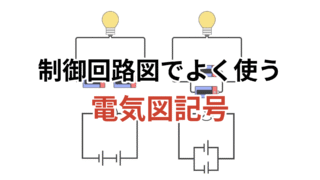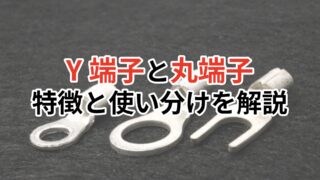電気を安全に使うために欠かせない装置といえば「ブレーカ」ですよね。
皆さんの家にも必ずと言っていいほど設置されているものなので、ブレーカという言葉は聞いたことはあると思います。
実はブレーカーにも種類があります。その代表が 配線用遮断器 と 漏電遮断器 です。
「どっちも電気を止めるんでしょ?」と思う方も多いかと思いますが、実は役割がまったく違います。
本記事では、「配線用遮断器」と「漏電遮断器」の違いについて初心者目線で解説します。

「配線用遮断器」と「漏電遮断器」は
見た目が似ているから違いが分かりにくいですよね!
配線用遮断器とは?(機器を守るブレーカ)
まずは「配線用遮断器」から。
これは家庭や工場の分電盤に必ずついている装置で、三菱電機製では 「ノーヒューズブレーカ(NFB)」、富士電機製であれば「オートブレーカ」 と呼ばれるものです。
主に、過電流による破損から配線内の電気機器を守る役割が配線用遮断器にはあります。
配線用遮断器の役割
過電流を遮断する
電気を使いすぎたとき、配線に流れる電流が増えて危険になるのを防ぎます。
例えばドライヤー・電子レンジ・エアコンを同時に使ったらブレーカーが落ちた…という経験、ありませんか?あれは配線用遮断器が過電流を検知して電気を遮断しています。
回路を構成している電線は、太さ・材質によって流せる電流の量が決まっています。
もし、規定以上の電流が流れ続けると電線が発熱し、最悪の場合発火して火災につながる恐れがあります。
こうした事故を防ぐ為に、配線用遮断器は過電流を瞬時に検知し、自動で電気を遮断してくれることで回路を守ってくれているんです。
短絡(ショート)を防ぐ
配線用遮断器のもう一つの役割は、短絡(ショート)から回路を守ることです。
電線同士が接触して一気に電流が流れる「短絡(ショート)」が起きると大事故につながりますが、これも瞬時に検知して回路を遮断することで安全を守ってくれます。
配線用遮断器の特徴
配線用遮断器は、過電流とショートを瞬時に検知してくれます。
つまり、火事や機器の破損を防ぐのがメインで、漏電には反応しません。また、配線用遮断器は過電流を検知して配線を遮断してくれる機能をもっていますが、回路上で過電流が発生している事には違いありません。
機器の寿命を長く保つためにも、過電流が発生させないことを意識しましょう。
漏電遮断器とは?(人を守るブレーカー)
次に「漏電遮断器」。こちらは 「漏電ブレーカー」 とも呼ばれます。
名前の通り、漏電が起きたときに回路を遮断するのが役割です。配線用遮断器に漏電検知機能を追加した感じです。
配線用遮断器は「機器や配線を守る」ためのものでした。対して漏電遮断器は「人や建物を守る」ためのものです。
漏電遮断器の役割
感電を防ぐ
本来、電気は電線や機器の中を流れるものです。しかし、様々な要因によって意図しない箇所に電気が漏れ出てしまうことがあります。これを漏電といいます。
漏電した箇所に人が触れると、感電してしまい大変危険です。
感電による災害を防ぐためにも漏電遮断器が使用されます。漏電遮断器はごく小さな漏れ電流でも検知し、瞬時に電気を止めてくれます。
漏電火災を防ぐ
漏電によって壁の中や機器の金属部分が熱を持つと、火災の原因になります。
漏電遮断器を設置することで、漏電火災のリスクを未然に防げるのも大きなポイントです。
漏電遮断器の特徴
漏電遮断器は、過電流とショート・漏電を検知して瞬時に検知してくれます。
配線用遮断器が「配線や機械を守る装置」なのに対して、
漏電遮断器は 「人の命や建物を守る装置」 といえます。
配線用遮断器と漏電遮断器の違い
ここまでの説明で、それぞれの役割がなんとなく分かってきたと思います。
では実際に、配線用遮断器と漏電遮断器にはどんな違いがあるのかを整理してみましょう。
まず大きな違いは、検知する異常の種類です。配線用遮断器は「電気の使いすぎ(過電流)」や「ショート(短絡)」を検知して電気を止めます。一方、漏電遮断器はそれに加えて「漏電」も検知して止めることができます。
つまり、
- 配線用遮断器:機器や配線を守るためのブレーカ
- 漏電遮断器:人や建物を守るためのブレーカ
という目的の違いがあります。
また、見た目が似ていても、内部構造は少し異なります。
漏電遮断器には「漏電検出用トランス(検出コイル)」が組み込まれており、電気の“行き”と“帰り”の電流に差があると「漏電が起きている」と判断して瞬時に電気を遮断します。
この仕組みのおかげで、感電や漏電火災を未然に防ぐことができるのです。
分電盤では、主幹部分に漏電遮断器(ELB)、各回路に配線用遮断器(MCB)が設置されているケースが多いです。
これにより、「漏電が起きたときは全体を遮断」「一部の過電流は該当回路だけを遮断」と、安全性と使いやすさの両立が実現されています。
まとめ

配線用遮断器と漏電遮断器、似ているようで違う用途・機能であることがわかりましたね。
- 配線用遮断器:機器を「過電流」や「短絡(ショート)」から守る
- 漏電遮断器:過電流や短絡とプラスして、「漏電」から人や建物を守る
家庭やオフィスの分電盤を見ると、主幹に漏電遮断器、その下に配線用遮断器が並んでいるのが一般的です。
つまり、両方そろってはじめて「電気を安心して使える環境」が整うというわけです。
電気は目に見えないからこそ、正しく理解して安全に使うことが大切。
この記事が初心者のみなさんにとって「ブレーカーの役割」を理解するきっかけになれば嬉しいです!